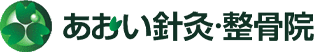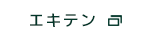- 症例
肩こりに鍼灸が効く理由を東洋医学で解説!効果と仕組みを紹介 名古屋市東区大曽根の肩こりの名医がお伝えする改善法

慢性的な肩こりに悩んでいませんか?
デスクワークやストレスが原因で肩のこりや痛みに悩む方が増えています。
そんな中、注目されているのが「鍼灸治療」です。
では、なぜ鍼灸が肩こりに効くのでしょうか?
本記事では、東洋医学の視点からその効果の仕組みをわかりやすく解説し、実際の治療法や予防のポイントまで詳しくご紹介します。
自然な方法で肩こりを根本から改善したい方は必見です。
目次
肩こり治療のご予約はこちらから https://page.line.me/663vgyjq?openQrModal=true
肩こりとは何か?その原因とメカニズム

現代人に多い肩こりの特徴
肩こりとは、首から肩、背中の上部にかけて感じる「重だるさ」「こわばり」「痛み」などの不快な症状を指します。
特に現代人に多いのが、長時間のデスクワークやスマートフォン操作による同じ姿勢の持続による肩こりです。
これにより筋肉が緊張し、血流が悪化して老廃物がたまり、コリや痛みが発生します。
さらに、運動不足や睡眠の質の低下、ストレスも肩こりを悪化させる大きな要因になります。
これらの生活習慣の乱れが積み重なることで、慢性的な肩こりへとつながっていきます。
筋肉疲労・血行不良・ストレスとの関係
肩こりの主な原因には、以下の3つが密接に関係しています。
■ 筋肉疲労
長時間の同じ姿勢や過度な筋肉の使用により、肩周辺の筋肉が硬直し、疲労物質が蓄積。
これが痛みや重だるさの原因になります。
■ 血行不良
筋肉が緊張し続けることで、血液やリンパの流れが滞り、酸素や栄養が届きにくくなります。
結果、筋肉の修復が遅れ、コリが慢性化します。
■ 精神的ストレス
精神的な緊張も筋肉の緊張を引き起こします。
ストレスが自律神経を乱し、筋肉を常に収縮させる状態が続くため、肩こりが改善しにくくなります。
肩こりは単なる「疲れ」ではなく、生活習慣や自律神経の乱れが関係する全身の不調のサインとも言えます。
次章では、この肩こりを東洋医学ではどのように捉えているかを詳しく見ていきましょう。
肩こり治療のご予約はこちらから https://page.line.me/663vgyjq?openQrModal=true
東洋医学から見る「肩こり」の考え方

気・血・津液の滞りがもたらす影響
東洋医学では、体の不調は「気(き)」「血(けつ)」「津液(しんえき)」のバランスが崩れることによって起こると考えられています。
-
気は生命エネルギーのようなもので、体をめぐる力そのものです。
-
血は栄養を全身に届ける役割を担い、津液は体内の潤い(水分)を保つ役割をしています。
この3つの巡りが滞ると、筋肉が栄養不足になり、冷えや張り感、こりが生じやすくなります。
肩こりはまさに、「気・血の巡りが悪くなった結果として現れる症状」とされます。
特に、気の不足(気虚)や気の滞り(気滞)、血の巡りが悪い状態(瘀血:おけつ)は、肩こりの原因としてしばしば登場します。
肩こりは「内臓の疲れ」からくることも
東洋医学では「肩こり=筋肉の問題」とは限らず、内臓の働きの不調が肩こりとして表面化すると考えます。
たとえば:
-
胃腸が弱ると気血が作られず、筋肉が栄養不足でこりやすくなります。
-
**肝(かん)**は血の貯蔵と流れをコントロールするため、肝の機能が低下すると、筋肉に十分な血が届かず、こりにつながることもあります。
-
ストレスが肝の気の流れを乱すことで、気滞となり肩周辺の張り感が強くなるケースも多く見られます。
このように東洋医学では、「肩こりは全身のバランスの乱れ」と捉え、単に表面の筋肉だけを診るのではなく、内臓や精神的な要因まで含めたアプローチを行います。
次章では、鍼灸がどのようにしてこうしたバランスの乱れに働きかけ、肩こりを改善していくのかを詳しくご紹介します。
肩こり治療のご予約はこちらから https://page.line.me/663vgyjq?openQrModal=true
鍼灸が肩こりに効く理由とは?

ツボ刺激による自律神経と血流の調整
鍼灸治療の最大の特徴は、「ツボ(経穴)」を刺激することで、自律神経のバランスを整え、全身の循環を改善する点にあります。
自律神経は、交感神経(緊張)と副交感神経(リラックス)によって体の働きをコントロールしていますが、ストレスや疲労が重なると交感神経が優位になり、筋肉が緊張して血流が悪化します。鍼灸はこの自律神経にアプローチし、リラックスモードへ導くことで筋肉の緊張を緩め、血流を促進します。
また、東洋医学では「気の流れ(気血の巡り)」を整えるという目的でツボを選びます。
滞った気を流すことで、肩の重だるさやこわばりが自然に和らぐのです。
筋肉の緊張緩和と自然治癒力の活性化
鍼(はり)が皮膚や筋肉に微細な刺激を与えることで、身体はそれを「微小な損傷」として認識し、自然治癒力(自己修復力)を活性化します。
この過程で以下のような作用が期待されます:
-
血行促進:筋肉内の血流が改善し、酸素や栄養が供給され、老廃物が流れやすくなります。
-
筋肉の緊張緩和:特に肩周辺の筋肉が過緊張している場合、鍼を刺すことでピンポイントに緊張をゆるめることが可能です。
-
痛みの軽減:鍼の刺激によってエンドルフィン(脳内の天然の鎮痛物質)が分泌され、痛みを自然に抑える効果もあります。
灸(きゅう)では熱を使って温めることで、冷えや血行不良の改善に役立ち、特に「冷えが原因の肩こり」には効果的です。
つまり、鍼灸は「外側の筋肉」に直接アプローチするだけでなく、「内側の循環や神経のバランス」も整えることで、根本的な肩こりの改善を目指す治療法なのです。
次章では、実際に鍼灸治療がどのように行われるのか、その流れと具体的なツボについて解説します。
肩こり治療のご予約はこちらから https://page.line.me/663vgyjq?openQrModal=true
実際の鍼灸治療の流れとポイント

問診から施術までの一般的な流れ
初めて鍼灸治療を受ける方は、「何をされるのか」「痛くないのか」など、不安を感じることも多いかと思います。
ここでは、鍼灸治療の基本的な流れをご紹介します。
【1】問診(カウンセリング)
最初に、現在の症状・生活習慣・既往歴などを詳しく聞き取ります。
東洋医学的な観点から、体全体のバランスを見極め、肩こりの原因を根本から探ります。
【2】脈診・舌診・腹診
脈の状態、舌の色や形、お腹の張りなどをチェックし、体の内側の状態を把握します。これにより、施術方針や使うツボが決定されます。
【3】施術(鍼・灸)
肩まわりを中心に、必要に応じて手足や背中などのツボにも鍼やお灸を行います。
【4】施術後のアドバイス
生活習慣・姿勢・セルフケアの指導を受け、再発予防にもつなげていきます。
よく使われるツボとその効果
肩こりに対しては、以下のようなツボがよく使われます。
それぞれのツボには特有の効果があり、症状や体質に応じて選ばれます。
■ 肩井(けんせい)
肩の真ん中にある代表的なツボ。
肩の緊張を緩和し、血流を改善する効果が高く、肩こりの定番ポイントです。
■ 天柱(てんちゅう)、風池(ふうち)
首の後ろ、うなじのあたりにあるツボ。
頭痛や眼精疲労を伴う肩こりに有効で、自律神経の乱れにもアプローチできます。
■ 合谷(ごうこく)
手の甲にある万能ツボ。
全身の気血の流れを促進し、痛みを和らげる効果があります。
首や肩のコリだけでなく、ストレスケアにも使われます。
鍼灸は「症状を取り除く」のではなく、「体の状態を整える」ことで結果的に症状を改善していくアプローチです。
次章では、鍼灸治療とあわせて行いたい、肩こり予防とセルフケアについてご紹介します。
肩こり治療のご予約はこちらから https://page.line.me/663vgyjq?openQrModal=true
肩こりを繰り返さないための予防法

日常生活でできるセルフケアと姿勢改善
鍼灸治療で肩こりが改善しても、日々の生活習慣が乱れていると再発のリスクは高くなります。
根本的な改善のためには、セルフケアの習慣化が欠かせません。
■ 姿勢の見直し
長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用で猫背になっていませんか?
肩こりを予防するには、背筋を伸ばして頭を前に出しすぎない姿勢を意識しましょう。
椅子やデスクの高さも調整すると◎。
■ 定期的なストレッチ・体操
1時間に1回は立ち上がり、肩や首を回したり、深呼吸をするなどの軽い運動を取り入れましょう。肩甲骨まわりの柔軟性を高める体操は特に効果的です。
■ 目の疲れ対策
目の疲れは肩こりに直結します。パソコン作業では**画面を見続ける時間を区切る(20分ごとに1分休憩など)**ことで目と肩の負担を減らせます。
定期的な鍼灸ケアのメリットと通院目安
肩こりを予防し、再発しにくい身体をつくるには、定期的なメンテナンスとしての鍼灸治療も有効です。
■ 鍼灸を「治療」から「予防」へ
肩こりがひどくなってから施術を受けるのではなく、症状が軽いうちや体調が崩れる前から通うことで、体の巡りを整えやすくなります。
ストレスが多い方や長時間のデスクワークをしている方には、月1〜2回の施術がおすすめです。
■ 継続による体質改善
鍼灸は一時的な対症療法ではなく、体質そのものを整えていく治療法です。
継続することで血流や自律神経の状態が安定し、肩こりを繰り返さない体づくりが可能になります。
肩こりは放っておくと頭痛や倦怠感、集中力の低下など、さまざまな不調を引き起こす原因になります。
鍼灸による定期的なケアと、日常生活に少しの工夫を取り入れることで、肩こり知らずの健やかな体を目指しましょう。
肩こり治療のご予約はこちらから https://page.line.me/663vgyjq?openQrModal=true